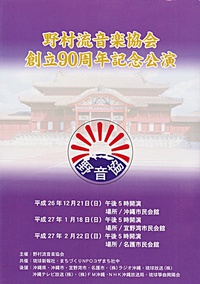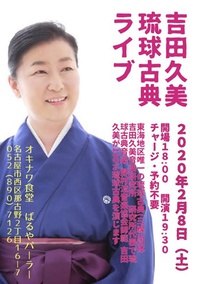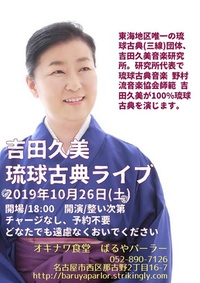2007年03月11日
春を呼ぶコンサート
三線も七年やってると、こういうステージの場合着替える場所がそんなに広くないことは見当がつく。黒留袖一式なんて持っていくのは大変だし、毎年恒例の川崎での沖縄芸能大会のように、着付けを手伝ってくれる人はあまりあてにできない。
で、最近そういう場合は「黒の紋付に袴」という男性と同じ格好でやることにしているのです。一度やってみたらそのあまりの快適さにハマった……
今回の場合、黒紋付だけ持っていって向こうで着替えればいいわけで、だったら黒紋付も着ていっちゃえば、と言われそうだけど、さすがのわたしも「宝塚の卒業式スタイル」で街を歩く勇気はないってば(激爆)。
いやでも袴スタイルって本当に楽ちん~。裾捌きを気にしなくてもいいし。明治時代の女学生が味わった開放感がよーくわかります。もっと日常の和装として普及してくれればいいのに。
で、話を戻してステージの報告。

「渡りぞう~瀧落・安波節・安里屋ユンタ」の幕開けから始まって、かぎやで風、四つ竹、谷茶前、くば笠、貫花、日傘踊り、前之浜、鳩間節というラインナップ。この合間に、沖縄の衣装の説明(四つ竹の衣装の着付け実演)があったり、楽器の説明があったり、みんなで歌おう沖縄民謡コーナーがあったりと、なかなか手作り感あふれるコンサート。
お客さんはひばりが丘近郊の地域住民が中心で、公民館への電話申し込みによる先着60名締め切り方式だったのだが、噂によれば受付開始から数時間で「満員御礼」になったとのこと。沖縄芸能に対する関心の高さがうかがえる。それだけに「みんなで歌おう沖縄民謡コーナー」でも、花、芭蕉布、涙そうそう、てぃんさぐの花、安里屋ユンタなど、会場の人も歌詞カード見ながら一緒に歌ってくれたのは気持ちよかった。
あ、ちなみにわたしは幕開けのほかに「貫花」「前之浜」の地謡に出演。民謡コーナーでは「花」と「涙そうそう」を歌いました。
最後は「きらく会」のエイサーでさらに盛り上がり。

フィナーレは例によって師匠の「唐船ドーイ」。加勢にかり出されたわたしはまた筋肉痛起こしかけました。やっぱり「カチャーシー・ア・ゴーゴー」のレベルははるかに遠かった。
で、最近そういう場合は「黒の紋付に袴」という男性と同じ格好でやることにしているのです。一度やってみたらそのあまりの快適さにハマった……
今回の場合、黒紋付だけ持っていって向こうで着替えればいいわけで、だったら黒紋付も着ていっちゃえば、と言われそうだけど、さすがのわたしも「宝塚の卒業式スタイル」で街を歩く勇気はないってば(激爆)。
いやでも袴スタイルって本当に楽ちん~。裾捌きを気にしなくてもいいし。明治時代の女学生が味わった開放感がよーくわかります。もっと日常の和装として普及してくれればいいのに。
で、話を戻してステージの報告。

「渡りぞう~瀧落・安波節・安里屋ユンタ」の幕開けから始まって、かぎやで風、四つ竹、谷茶前、くば笠、貫花、日傘踊り、前之浜、鳩間節というラインナップ。この合間に、沖縄の衣装の説明(四つ竹の衣装の着付け実演)があったり、楽器の説明があったり、みんなで歌おう沖縄民謡コーナーがあったりと、なかなか手作り感あふれるコンサート。
お客さんはひばりが丘近郊の地域住民が中心で、公民館への電話申し込みによる先着60名締め切り方式だったのだが、噂によれば受付開始から数時間で「満員御礼」になったとのこと。沖縄芸能に対する関心の高さがうかがえる。それだけに「みんなで歌おう沖縄民謡コーナー」でも、花、芭蕉布、涙そうそう、てぃんさぐの花、安里屋ユンタなど、会場の人も歌詞カード見ながら一緒に歌ってくれたのは気持ちよかった。
あ、ちなみにわたしは幕開けのほかに「貫花」「前之浜」の地謡に出演。民謡コーナーでは「花」と「涙そうそう」を歌いました。
最後は「きらく会」のエイサーでさらに盛り上がり。

フィナーレは例によって師匠の「唐船ドーイ」。加勢にかり出されたわたしはまた筋肉痛起こしかけました。やっぱり「カチャーシー・ア・ゴーゴー」のレベルははるかに遠かった。

Posted by 唯ねーねー at 16:36│Comments(0)
│ステージ