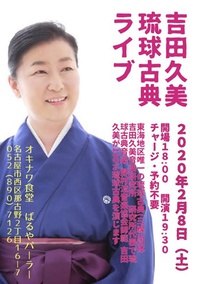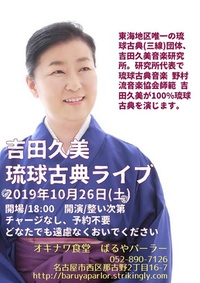2007年10月08日
なんちゃってスディナ
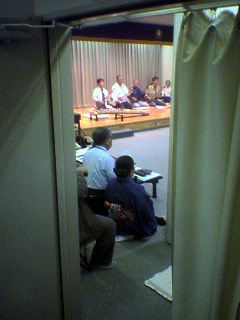
(地謡の練習風景。カーテンの向うで踊り手さんたちが練習してます)
昨日は来週の「沖縄芸能大会」の最終リハーサル。
わたしの出番は第一部幕開け(かぎやで風~ごゑん節~辺野喜節)、第二部幕開け(百名節~白鳥節~立雲節)、そして器楽合奏(松本節~中作田節~江佐節)。第二部の幕開けの曲はいままで歌ったことがなかったし、器楽合奏の曲もいつもの歌い方とパターンが違うしで覚えきれるか心配だったけど、なんとか暗譜完了。やっぱり本番に強いタイプらしい(笑)。
昨日はお天気もよかったので、「なんちゃってスディナ」を着てお出かけ。
いやこれがなかなか好評でした。


実はこれ、一月に開催された仲宗根忠治先生の85歳の祝賀会の時に余興ステージで使った衣装なのです。
たまたま、ヤフーオークションでちょっと琉球絣っぽい紺の木綿の着物が出品されてたので、それをめでたく710円で落札。昔の八重山の女性の正装「スディナ」に似た形に改造。
スディナを一から作るのは和裁の知識がないので無理だけど、ヤマトの着物を改造するくらいなら簡単。
ただしこの場合、改造するのは裏地のない単衣(ひとえ)と呼ばれるタイプに限ります。袷は面倒なので……
1.まず袖口をほどいて袖丈を詰め、ゆったりとした筒袖の形に直す。
(琉球の着物とヤマトの着物の大きな違いは袖口。ヤマトでも十二単の袖口なんかは開いていますが)
2.裾を短くちょん切る。(長さは膝下10cmくらいかな)
3.両脇をほどいてスリットの形に縫い直す(ベトナムのアオザイみたいな形)
4.両脇に紐(甚平や作務衣みたいに)をつけて完成
祝賀会のステージでは、脇のスリットを縫い閉じて、紫のモス布を帯代わりに腰に巻いた。これでエイサーの手踊りネーネーの出来上がり(笑)。 脇を縫い閉じるなんてすぐできるので、必要があればいつでもこの形に戻すことができる。そこがミソ。
本来の八重山のスディナは脇の「身八つ口」がない。普通の着物を改造する場合は、わざわざ縫い閉じるのは面倒なので、袖丈を身八つ口と同じ位の長さに詰めるだけでそこはいじらない。だから「なんちゃってスディナ」なわけ。
本来ならカカン(下袴)という白いプリーツスカートのようなものをはくのですが、あいにく持ち合わせがないので(今度沖縄に行ったときにでも買いに行こう)、アオザイの下にはく白いワイドパンツをはいてみた。ぴったり。
じつはこのスタイル、帯を締めないし、あぐらかいたり立膝ですわったりもできるので、すごくラクチンなのです。夏は風が通るので浴衣より着ていて涼しい。
ヤフオクにはよく昔の着物が出品されてるけど、昔の人は身長が低かったので丈の短いものが多く、こういうのは今の人でも着られる丈の長いものに比べて格安。今回ので味をしめたので、またいい着物を捜して作ってみようかと思ってます。
Posted by 唯ねーねー at 11:00│Comments(0)
│DIY