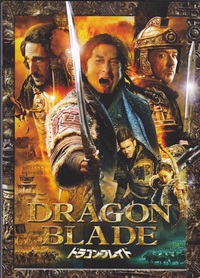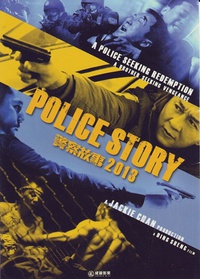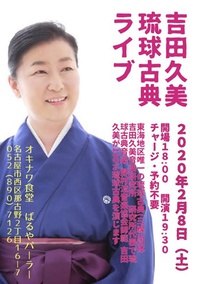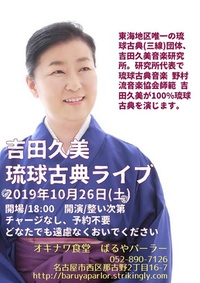2011年07月02日
京の五条の橋の上……

昨日は茂山千五郎家の狂言の会「お豆腐の和らい」に行ってきました。
(なぜ「お豆腐」なのかは茂山千五郎家のホームページを見てね)
狂言をはじめて見たのは小学生の時。学校の行事で「末広がり」という狂言を見た記憶と、途中で寝てしまった記憶が鮮明に……

やっぱ小学生じゃ、あの面白さを理解するのは無理でした(笑)。
で、この「お豆腐の和らい」は初心者向けの解説つきの上演で、演目の合間に「通訳」が登場してそれぞれどんなお話か解説してくれるのですが、時には本編よりこっちのほうが面白かったりして……

この日の演目は「八幡前」「吹取」「萩大名」。
「八幡前」は一芸にひいでたムコさん募集中の金持ちのところに立候補するため、知り合いの諸芸の達人に即席でなんか芸を教えてもらおうと頼み込む調子のいい男のお話。
「吹取」は婚活にいそしむオッサンが、清水寺の観音様に願掛けして「月夜の晩に五条橋に行って笛を吹いたら妻をさずけてやる」というお告げをもらって……という話。
「萩大名」は訴訟の件で都に滞在している大名が、従者の太郎冠者が紹介してくれた立派な庭を持っている資産家の庭の萩を見せてもらいに行くことになり、その場で読まなきゃいけない和歌を太郎冠者に教えてもらうが物覚えが悪くて……という話。
「八幡前」と「萩大名」はセリフオチなので、今となってはちょっと笑うのは難しいのですが、「吹取」は爆笑でしたねぇ。
主人公(シテ)のオッサンはせっかくお告げをもらったものの笛が吹けない。知り合いの笛の名人に頼み込んで、一緒に五条橋に行ってもらって代理で笛を吹いてもらうんですが、この辺の笛名人とのやりとりも面白かったし、笛の音にこたえて女性が出てきたものの、その笛名人のほうに寄っていってしまうのを「この人は代理だから」と自分の方に引き戻すオッサンの必死ぶりも笑える。
で、いざご対面、と恥ずかしいのか嫌がる女のかぶっていた衣を取り除けてみると、中から出てきたのはお多福……(ま、そんな感じのお面をかぶった女性です)
ひと目見た瞬間から手のひら返したように「あなたが吹いた笛で出てきたんですから」と笛名人にその女性を押し付けようとするオッサン、「いやいやわたしにはすでに妻が」と辞退する笛名人、この辺もわかりやすくて笑えるところ。
この話、展開はまったくのコメディなんですが、その背景探ってみるとなかなか深くて怖い。
上演前に「通訳」も言っていましたが、夜に口笛を吹くと蛇が来るとか魔物が来るとかいう言い伝えがあって、夜に笛を吹くと異世界のものを呼び寄せてしまう、という概念があるそうなんです。
(五条橋に現れる牛若丸が笛を吹いてるのは、あれはいわば魔物とみなされた弁慶に対する挑発行為)
たまたま狂言を見に行く前に小松和彦の「日本魔界案内」「京都魔界案内」とか読みまして、「あっ」と思った点多数。


この「吹取」に出てくる「清水の観音」と「五条橋」がまた尋常の組み合わせじゃないんですよね。
まず清水観音。今では境内の「地主神社」にすっかりお株を奪われた感あるけど、もともと清水の観音様も縁結びのご利益あらたかで、それにまつわる話は「物ぐさ太郎」「小男の草子」などいろいろ残っています。
それから、清水寺の周辺は実は「鳥辺野」と言って、昔の風葬の地。
清水寺から五条橋方面に行く途中の六道珍皇寺はあの世への入口があると言われるお寺だけど、それはこの寺がやはり鳥辺野の入口にあったからで、その延長線上にある五条橋も一種の「あの世への入口」だったわけです。
(もともと橋というのは民俗学的にも異界とつながる空間的意味合いが強い)
そういえば映画「五条霊戦記」に出てきた五条橋も相当に妖しい空間だったなぁ……
映画の評価はわたし的には「星ひとつ」でしたが。
そんなところで笛吹いて呼び出しちゃった女性、となると、考えようによってはかなり怖い代物だと思うんですよね。
まぁ縁結びそのものが、本当はいちかばちかの大博打、ということなのかもしれません(笑)。
それから今回狂言を見ていていやがおうにも目に付いたのは、演者のみなさんの立ち居振る舞い。
登場する時のあの腰は引き気味、上体は前傾気味、重心を前に持ってきてすり足……という歩き方(「かぎやで風」の練習でさんざん稽古したあの動きに似てる)とか、長袴の裾のさばき方とか立ったり座ったりする時の動きとか、いまや日常生活ではほぼ絶滅しちゃった動きですものね。
伝統芸能の中でこういう動作を保存していくのって、ある意味大事なことなんだろうなぁ。
いや他人事じゃなくって、わたしもああいう風にごく当たり前のように立ったり座ったりできるようになりたいんですが、いまだに正座は苦手だ……
「八幡前」は一芸にひいでたムコさん募集中の金持ちのところに立候補するため、知り合いの諸芸の達人に即席でなんか芸を教えてもらおうと頼み込む調子のいい男のお話。
「吹取」は婚活にいそしむオッサンが、清水寺の観音様に願掛けして「月夜の晩に五条橋に行って笛を吹いたら妻をさずけてやる」というお告げをもらって……という話。
「萩大名」は訴訟の件で都に滞在している大名が、従者の太郎冠者が紹介してくれた立派な庭を持っている資産家の庭の萩を見せてもらいに行くことになり、その場で読まなきゃいけない和歌を太郎冠者に教えてもらうが物覚えが悪くて……という話。
「八幡前」と「萩大名」はセリフオチなので、今となってはちょっと笑うのは難しいのですが、「吹取」は爆笑でしたねぇ。
主人公(シテ)のオッサンはせっかくお告げをもらったものの笛が吹けない。知り合いの笛の名人に頼み込んで、一緒に五条橋に行ってもらって代理で笛を吹いてもらうんですが、この辺の笛名人とのやりとりも面白かったし、笛の音にこたえて女性が出てきたものの、その笛名人のほうに寄っていってしまうのを「この人は代理だから」と自分の方に引き戻すオッサンの必死ぶりも笑える。
で、いざご対面、と恥ずかしいのか嫌がる女のかぶっていた衣を取り除けてみると、中から出てきたのはお多福……(ま、そんな感じのお面をかぶった女性です)
ひと目見た瞬間から手のひら返したように「あなたが吹いた笛で出てきたんですから」と笛名人にその女性を押し付けようとするオッサン、「いやいやわたしにはすでに妻が」と辞退する笛名人、この辺もわかりやすくて笑えるところ。
この話、展開はまったくのコメディなんですが、その背景探ってみるとなかなか深くて怖い。
上演前に「通訳」も言っていましたが、夜に口笛を吹くと蛇が来るとか魔物が来るとかいう言い伝えがあって、夜に笛を吹くと異世界のものを呼び寄せてしまう、という概念があるそうなんです。
(五条橋に現れる牛若丸が笛を吹いてるのは、あれはいわば魔物とみなされた弁慶に対する挑発行為)
たまたま狂言を見に行く前に小松和彦の「日本魔界案内」「京都魔界案内」とか読みまして、「あっ」と思った点多数。


この「吹取」に出てくる「清水の観音」と「五条橋」がまた尋常の組み合わせじゃないんですよね。
まず清水観音。今では境内の「地主神社」にすっかりお株を奪われた感あるけど、もともと清水の観音様も縁結びのご利益あらたかで、それにまつわる話は「物ぐさ太郎」「小男の草子」などいろいろ残っています。
それから、清水寺の周辺は実は「鳥辺野」と言って、昔の風葬の地。
清水寺から五条橋方面に行く途中の六道珍皇寺はあの世への入口があると言われるお寺だけど、それはこの寺がやはり鳥辺野の入口にあったからで、その延長線上にある五条橋も一種の「あの世への入口」だったわけです。
(もともと橋というのは民俗学的にも異界とつながる空間的意味合いが強い)
そういえば映画「五条霊戦記」に出てきた五条橋も相当に妖しい空間だったなぁ……
映画の評価はわたし的には「星ひとつ」でしたが。
そんなところで笛吹いて呼び出しちゃった女性、となると、考えようによってはかなり怖い代物だと思うんですよね。
まぁ縁結びそのものが、本当はいちかばちかの大博打、ということなのかもしれません(笑)。
それから今回狂言を見ていていやがおうにも目に付いたのは、演者のみなさんの立ち居振る舞い。
登場する時のあの腰は引き気味、上体は前傾気味、重心を前に持ってきてすり足……という歩き方(「かぎやで風」の練習でさんざん稽古したあの動きに似てる)とか、長袴の裾のさばき方とか立ったり座ったりする時の動きとか、いまや日常生活ではほぼ絶滅しちゃった動きですものね。
伝統芸能の中でこういう動作を保存していくのって、ある意味大事なことなんだろうなぁ。
いや他人事じゃなくって、わたしもああいう風にごく当たり前のように立ったり座ったりできるようになりたいんですが、いまだに正座は苦手だ……

Posted by 唯ねーねー at 17:46│Comments(0)
│みるきくよむ